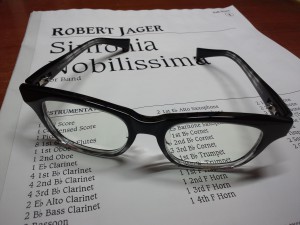2013年10月
…とは「コードネーム」、どんな和音かを表す名前のひとつです。
西洋音楽における和音の基本は「ド」「ミ」「ソ」。
ですが、ディミニッシュの音の並びは「ド」「ミ♭」「ファ♯」「ラ」。
個人的には、長調にも短調にも縛られない感じがします。
とても不思議な響きのする和音です。
それぞれの音の間隔が1音半ずつ。
ですので、根音(ベースとなる音)は、
「ド」でも「ミ♭」でも「ファ♯」でも「ラ」でもいいのです。
実は、せせらぎでは、しょっちゅう「ディミニッシュもどき」を練習しています。
「ドレミファソラシド」の音階練習の後、
「ド」からスタートする人、
「ミ」からスタートする人、
「ソ」からスタートする人に分かれて、
それらを一斉に鳴らすという音階練習をします。
すると、
最初に響くのは「ド・ミ・ソ」の和音、
次に響くのは「レ・ファ・ラ」の和音、
という具合。
7番目に鳴るのは「シ・レ・ファ」。
音の間隔が1音半ずつ。
あと「ラ♭」が加わればディミニッシュの完成、となる訳です。
私にとってディミニッシュが印象に残る曲として
『コーラスライン』が挙げられます。
今回、『シンフォニア・ノビリッシマ』を読んでいて分かったのが、
この曲もディミニッシュを多用しているということ。
重厚さの中にも、何かポップな感じがするのは、
このディミニッシュのおかげかも知れません。
和音の進行があまりにも気持ちいいので、
ついつい鍵盤で弾いて遊んでいます。
禁煙2013年10月26日
ある呑み会で、
トランペット・コルネット・フリューゲルホルン奏者のF地くんが、
禁煙を宣言した。
正確に言うと、周りの我々が宣言させた。
F地くん、実はみんなが心配していることがある。
酒を飲まない、いや、飲めないにもかかわらず、
健康診断で出る肝臓の数値が悪いのだ。
俺なんか、浴びるほど飲んでいるのに肝臓の数値は正常なのだ。
肝臓に負荷をかけるのは、飲酒だけではないのだろうか?
※※※
そんなこんなでヘビー・スモーカーのF地くんは、
たばこを吸わなくなって50日になった。
これは、凄いことだ!
もしかすると、たばこを吸うか吸わないかなんてこと、
演奏への影響なんか微々たるものと思う方もおられるかもしれない。
が、私はそうは思わない。
ほんのちょっとのことと思えることでも、
積み重ねることによって、
その人のプレイに影響を及ぼしてくると思う。
F地くん、禁煙に賭けたその心意気、カッコいいぞ。
お化けみたいな視聴率を叩き出したTBSのテレビドラマ『半沢直樹』。
サラリーマンのドラマで、あまりに身につまされる思いがしてしんどかった。
そんな風に書くと、私自身もスーパー・サラリーマンのように思われるかも知れないが、
実際の私は「なんちゃって(※)サラリーマン」なのだ…
(※)なんちゃって、とは、「適当な」とか「いい加減な」という意味で使わせてもらっています。
もはや死語かも知れませんが…
でも、本当に観ていてしんどかった。
つまり、サラリーマンなら何がしか心に引っ掛かるものがあるドラマだったのだと思う。
近所の酒房「たなかや」が、
何のご縁か知らないが原作者の池井戸潤さんと知り合いだそうだ。
世間は狭い。
『半沢直樹』を全話観たのでもあるし、
ここは一つ、池井戸潤さんの本を何か読んでみようと思い立った。
何の気なしに読み始めたのが『下町ロケット』だ。
(直木賞受賞作とは読み終わるまで知らなかった)
どこか『半沢直樹』に似ているな、と思いながら読み進んだ。
理不尽な横槍や、明らかな営業妨害が挟み込まれることなど。
しかし、東京都大田区の中小企業がロケットの核となる部品供給に社運を賭ける様を観ていると、
京都市の名もない市民バンドが何とかいい演奏をしようともがいている様とだぶってくる。
モノ作りに賭ける情熱は同じなのだと思う。
物語の最終盤を読んでいたのは、出勤の阪急電車の車中。
思わず号泣してしまった。
クロスシートならまだ良かったが、ベンチシートの車両だった。
変な奴だと思われただろうな、いつものことだが…
何か、心に火がついたような感じがする。
選曲のこと2013年10月23日
演奏会後にアンケートを読ませてもらうと、
聞き覚えのある曲を聴きたい、
誰もが知っている曲を聴きたいという意見がやっぱり多いですね。
まぁ、充分に想像がつく答えです。
が、意外にも、
全然知らない曲に感興があったという感想を聞くこともあります。
例えば、
昨年の演奏会で採り上げた『エピソード・ファイブ』。
5拍子という、普段の生活の中であまり馴染みのない拍子で貫かれています。
吹奏楽のために書かれた曲で、
聴きに来てくださった方々の99.9%はこの曲を知らなかったと思います。
けれども、
「1本の映画を観ているようで面白かった」
という感想を聞かせてくれた人がいたのです。
この演奏会で最も印象に残ったのは『組曲「宇宙戦艦ヤマト」』だったけど、
その次に『エピソード・ファイブ』が凄く良かったと言ってくれたのです。
人の心に訴えかけるのは何なのか?
それは人それぞれで、
一つの決まった答えはないんだなぁ~、
と考える今日この頃です。
10月18日(金)。
いつものように音階練習からスタートしていきます。
この日は実音Aから始まる長調の音階でいろんなことをします。
(せせらぎでは「 “ A ” の音階で」などという言い方をしますが、
学校の音楽の授業風に言えば “ イ長調 ” の音階です)
フルートなど、C管の楽器にとっては、ラから始まり、♯が3つ。
F管のホルンとイングリッシュホルンにとっては、ミから始まり、♯が4つ。
トランペットやクラリネットなど、
吹奏楽で圧倒的多数派を占めるB♭管にとっては、
シから始まり、♯が5つ。
E♭クラリネット、アルト・サックス等のE♭管にとっては、
ファ♯から始まり、♯が6つ。
あるいは、
ソ♭から始まり、♭が6つ。
このように、Aの音階というのはとても厄介なのです。
が、管弦楽のチューニングで用いられるのは、この「A」の音。
なんででしょう?
非常に合わせにくい音階ですが、
かといって無視する訳にもいきません。
楽曲中にはありとあらゆる音階が登場するのですから。
ホルンのMくんの息の流れに乱れがあるなと思ったので、
注意するように指摘。
このときに顕著だったのがMくんの音だったのですが、
息の乱れは誰にでもあること。
この注意が他の皆さんにも伝わったのだと思います、
スムーズないい息の流れている音になりました。
ユニゾンでの音階練習から、
和音に分かれつつの音階練習に移行してから、
特に良くなりました。
きっと、ユニゾンの時よりも「よく聴く」注意力を必要とするからだと思います。
終止形(カデンツ)を用いての
クレッシェンド & デクレッシェンドの練習。
もう1年以上取り組んできたでしょうか。
数年前から、
音量の変化をつける際に、
音の高さ(ピッチ)まで動いてしまう、
特に音を小さくしていく時の動きが大きいと思っていました。
これは矯正しなくちゃ、と思って始めたのでした。
この日は難しい「Aの音階」を用いているにもかかわらず、
とてもうまくいっていると思いました。
着実に効果は上ってきているようです。
ただし、気をつけなければならないのは、
これは基本練習の時間から参加できていたメンバーでの音だった、
ということです。
全員集合が難しい宿命のもとでやっていかねばならない私たちにとり、
地味で地道な練習は永遠に続く課題なのです。
文化とは?2013年10月19日
酒房「たなかや」に、
スイスからのお客さんが来ていました。
私は途中参加だったのですが、
「漆器」についてのお話だったようです。
しきりに「日本文化」を賞賛しておられたのですが、
はてして「文化」とは何ぞや?
と、ふと考えてしまったのでした。
※※※
私が高校生だった頃、
『超時空要塞マクロス』というアニメーションが時代を席巻しました。
圧倒的な軍事力をもって地球に来襲した異星人・ゼントラーディが、
なぜか非力な地球に手を出すことができないのです。
それは、地球人が「文化」を持っているからでした。
彼らには、「文化」を持つ種族と関わってはならない、
という言い伝えがあったのです。
ゼントラーディは戦闘をするためだけに生み出された人工的な種族で、
「文化」というものを知らされていないのでした。
“ 歌 ” すらも知らない彼らは、
地球人のアイドル歌手リン・ミンメイの歌声に魅せられ、
次第に戦う意欲をなくしていきます。
遂には戦争をやめ、
地球人と共生する道を選びます。
“ 歌 ” の力で戦争が終結するという、
画期的なストーリーだったのです。
(ただし、なおも戦おうとする者たちに、
歌を聴かせてひるませておきながら、
反応兵器という呼称を与えられた、
実は核兵器を浴びせて殲滅するという、
恐ろしい設定もあったのですが…)
※※※
『超時空要塞マクロス』で、
ゼントラーディが文化と触れ合ったときの衝撃が、
“ カルチャー・ショック ” という言葉で表現されました。
「たなかや」で日本文化に触れたスイス人の青年も、
きっと “ カルチャー・ショック ” を受けたのだと思います。
では、“ ショック ” を受けるほどの“ カルチャー ” って何なのでしょう?
私は、“ 心騒ぐもの ” ではないかと考えています。
「文化」を横文字で書くと「culture」。
「agriculture」は農業。
土を耕すのが農業なら、
文化とは、心を耕すもの、と言えなくもないのでは。
せせらぎも、
小さな力かも知れないけれど、
「文化」に関わる活動をしているのだ。
と、思いたいですな。
急に涼しくなりましたな。
というか、朝晩なんか寒いくらい。
皆さま、体調を崩したりしておられませんか?
じっとしているだけで汗がダラダラ流れ落ちる猛暑と違い、
涼しいと調子いいもんだから、
ついつい練習をし過ぎてしまいませんかな。
こういう時こそ、一歩立ち止まり、
少しペースを落としたほうが安全かも知れませんな。
サボり奨励と受け取ってもらってOKです。
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」などと申しますから…
※※※
突然話が変わりますが、
自宅の近所に「たなかや」という、
昼はカフェで夜は酒房となる店があります。
時々、お店を飛び出し、鴨川の河川敷で呑み会を開かれます。
客がそれぞれ飲み物と食べ物を持ち寄り、
ざっくばらんに寄り集まろうという会。
これまで仕事の都合などで行くことができなかったのですが、
今回は10月14日(月)の体育の日に開くとのこと。
夜勤明けなので、体がもつ限りは呑めるな、
ということで初参加してきました。
これがその時の写真です。

夕方4時頃から呑み始めたのですが、
おいしくておいしくて、ハイ・ペースで呑みすぎました。
川風のせいもありだんだん寒くなってきました。
そして夜勤明けなので猛烈な睡魔に襲われました。
このままうたた寝したら危険やなと思ったので早目に帰ることにしたのですが、
いや、ホントに冷え冷えでした。
京都府南丹市美山町にある「観光農園江和ランド」から、
「10月13日(日)に創立20周年の記念式典を開くので、演奏で盛り上げてもらえないだろうか?」
という依頼を受けました。
確か、9月の上旬から中旬にかけてだったと思います。
準備期間一ヶ月というのはあまりに厳しい依頼だと思いましたが、
お世話になっている江和ランドさんからの依頼なんだから、
K団長を中心に何とかご要望に応えようと努力しました。
フルバンドでの演奏を希望しておられる訳ではなく、
アンサンブル形態を希望しておられる由。
こういった規模の依頼演奏をお受けする場合、
これまではフルートやクラリネットやサックス等の木管アンサンブルが多かったのですが、
今回は演奏場所が野外だということもあり、
金管楽器でアンサンブルを組むことになりました。
(木管楽器は直射日光を受けたりすると傷む危険があるのです)
トランペット=3人
ホルン=2人
トロンボーン5人
テューバ=2人
合計12人の楽員が志願してくれました。
僅か2回しか練習機会が作れませんでしたが、
何とか形作ってくれました。
(私はその練習には参加できていないのですが…)
10月13日(日)。
ようやく夏から秋に変わったかな?と思える清々しい朝。
早朝から、一路、美山を目指しました。
(私は応援&取材のためK団長の車に乗せてもらって同行)
国道162号線で京北・美山へと向かうのですが、
途中、先日の台風18号で落橋したと思われる箇所を迂回したりしつつ、
まずは集合地点の「美山町かやぶきの里」で全車集結。

《 朝日を受けて綺麗です》
それにしても、以前は私も喜んで車を運転していたものですが、
もう、あきまへんな。
乗せてもらうのがホントにありがたいです。
今回の4台のドライバーの方々、ありがとうございます。
(ちなみに、帰路、私はK団長の助手席でグースカ眠りこけてしまいました。
どうも済みません…)
※※※
江和ランドさんにお世話になっていると先述しましたが、
9年前に楽団の合宿でお邪魔したのが最初だと思います。
最初に江和ランドさんを見つけたのは、
確かトロンボーン・チームだったと記憶しています。
2月に行う楽団内のアンサンブル発表会がスタートしたばかりの時期で、
各パートともかなりの入れ込み様でした。
トロンボーン・アンサンブルを合宿練習するために江和ランドさんを探し当てた筈。
当初はトロンボーン・チームだけで行くことになっていたのが、
私のアドヴァイスが欲しいということで誘いを受け、
さらに他のパートも同行させて欲しいと話が広がり、
結局、20~25人くらいで行ったのではないでしょうか。
私たちが行ったのは雪深い真冬の美山。
雪の中でロングトーンをする人、
コテージの中でひたすら細かい音型をさらう人、
思い思いに個人練習して、
それからグループ毎に集まってアンサンブルの練習。
当時はまだホルンを吹いていた私も金管五重奏チームに参加していて、
思う存分練習させてもらいました。
「観光農園」なので、本来ならぶどう狩りなどを楽しませてもらうのでしょうが、
そういうのは一切ナシ。
が、夕食はとってもおいしい牡丹鍋!
酒も旨い!
そのあと、自然発生的な雪合戦へとなだれ込み、
「自爆!」などと訳の分からないことを喚きながら雪山に突っ込む指揮者がいたり…

《 かつて泊ったことのあるコテージです 》
私が参加したのは、その後もう一回だけだったと思いますが、
他の楽員さんはしばしば合宿に行かれました。
近所迷惑ってものを全く気にせず楽器の練習ができますから。
今回、お声掛けいただいたのは、こんないきさつがあったからです。
※※※
下の写真が創立20周年記念式典の会場です。

ここで本番の演奏を行いました。

《 本番中は録音に専念して撮影できず。これはリハーサル風景 》
江和ランドさんに一番お世話になったのは、
やはりトロンボーンの皆さんではないかと思います。
今回の志願者が最も多かったこともあって、
トロンボーン・チームは単独のアンサンブル演奏を2曲披露なさいました。
あとは金管楽器12人によるアンサンブル。
いずれも少ない練習で、よくまとめられたと感じました。
人数が少なくて、かつ、ベルが後ろを向いているホルンのお二人は、
音が聞こえるかどうかをさかんに心配しておられましたが、
全くその心配は当たりませんでした。
むしろ、山間のこの環境にホルンの音色はピッタリでしたな。
30℃クラスの暑さが続き、
地球は本当に大丈夫なのか?と思ってしまう10月11日(金)。
(雨が降って蒸し暑さが倍返し、いや倍増したようだ)
この日は『シンフォニア・ノビリッシマ』の初合奏。
この曲を「聴いた」ことはあっても「演奏」したことはない、という方が約半数。
そういったものなのだろう。
とにかく、まずは通してみた(一回止めたけれども)。
悪戦苦闘だった。
やはり油断大敵だ。
次に、曲頭から少しずつさらい直していった。
各部分におけるメロディ・和音・装飾音型群・低音などに切り分け、
それぞれの役割がクリアになるようにし、
その後、全員で合わせてみる。
まだ初合奏なので、まだまだ引っ掛かってしまう音型も多いが、
それでも一回目に通した時よりは明らかに鮮明になった。
今回、特に気をつけたのは、オーバーブローの抑制。
例えば、旋律を吹いているとき、
抑揚をつけようとして息の流れが変わる。
それ自体は問題ないのだが、
「ブオーッ」という感じの吹き過ぎになることがある。
これは聴いていてあまり美しくない。
息の「乱流」が起こらないよう気をつけようと呼びかけ続けた。
文字通り、同じ音型を担当する人同士で「息を揃え」ようということ。
かなり意識しないと難しいと思うが、
練習し続けていけばきっと効果があると思う。
個人練習も大切だが、
やはり楽員が揃って合奏するというのも大事だな、
と改めて思う。
※※※
さて、この日の合奏に間に合わないかと思われた老眼鏡、
何とか間に合った。
滲んで見えない音符の解析に早速役立った。
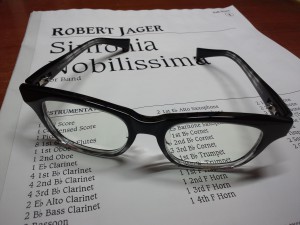
映画がはけた後、ふと女性二人の会話が耳に入ってきた。
OLか女子大生かといった風情。
映画のパンフレットを買っても、
そのあとに入ったカフェでペラペラめくりながら映画の振り返りのネタになるくらいで、
もう二度と開くことはないよね、っていう話。
へぇ~、パンフってそんなもんなんや、
と私にとっては意外な話だった。
私は映画鑑賞後、9割以上はパンフを買って帰るのだ。
市原隼人・上野樹里主演の映画『虹の女神』(2006年)を観たあと、
時間の都合もあってパンフを買わなかった。
が、その後、ロケ地のことなどが気になり、
どうしてもパンフが読みたくなった。
仕事帰り、
もう今からはレイトショウすらもかからないという遅い時間にTOHOシネマズ二条に着いて、
なんとかパンフを買うことができたのだった。
私が必ずと言っていいほどパンフを買うようになったのは、これ以来だ。
パンフを買うだけの目的で映画館に足を運ぶのも面倒くさいので…
先述のように、どこでロケしているんだろう?
どんな監督が撮っているんだろう?
ちらっと出てきただけの俳優さん、どっかで見たことあるけど、誰だっけ?
よく分からない映画だったが、制作者の意図は何だったの?
などなど、気になることがいっぱいあるのだ。
また、映画を一回観て、それで終わり、ではなく、
パンフを読むともう一度反芻できたりする。
映画を深く味わうことができて楽しいのだ。
なお、私は映画業界の回し者ではない。
« 古い記事