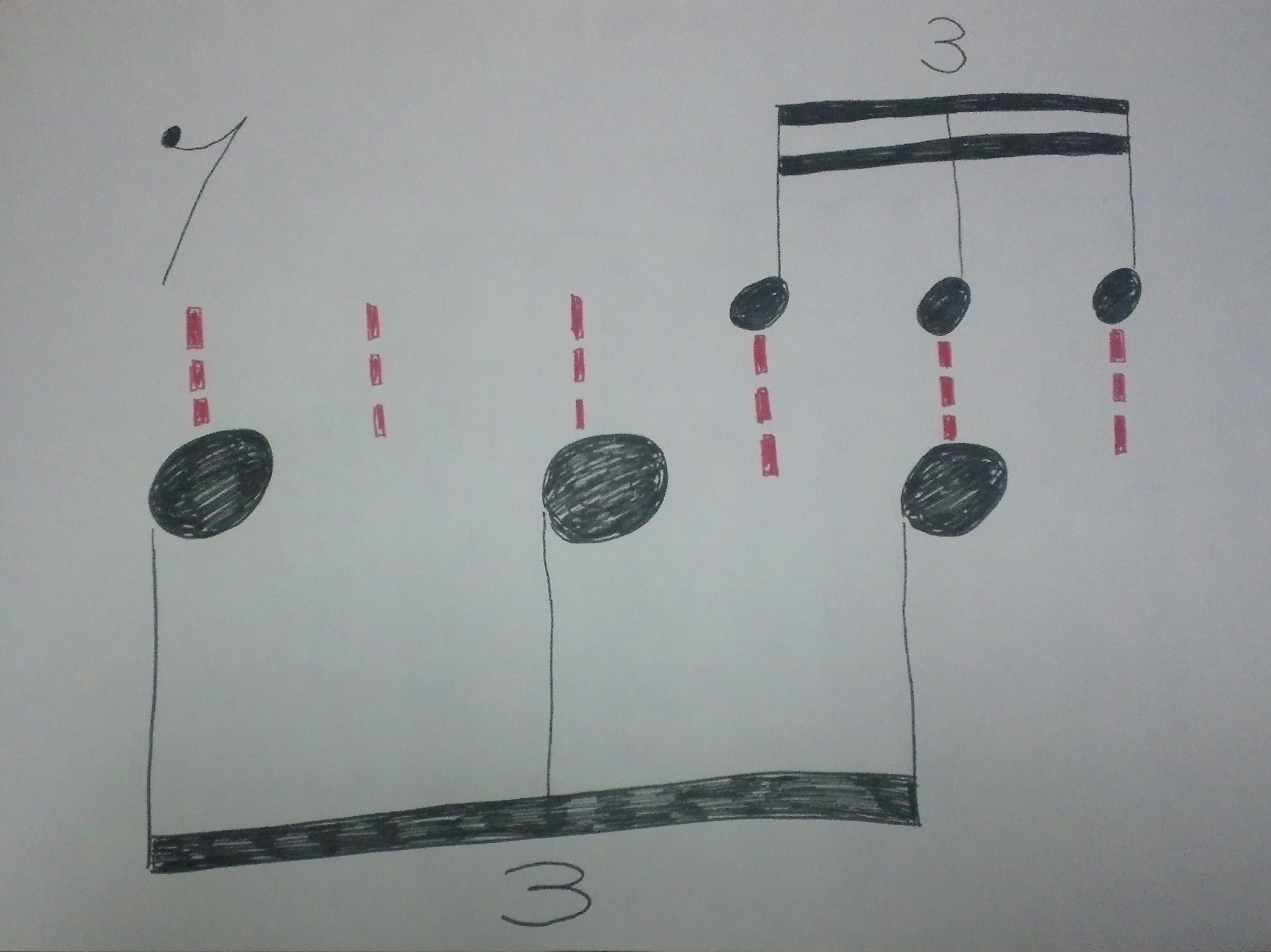三連符2016年10月23日
10/21(金)は、
日本シリーズの準備をしていたところに、
鳥取での地震が発生。
仕事が終わらず、合奏に参加できませんでした。
申し訳ありません。
この日は『北海の大漁歌』と『GR』の練習を予定していました。
副指揮者の K さんも合奏に行くことができませんでした。
役員のどなたかに指揮していただいたことと思います。
どんな練習になったでしょうか。
ところで、前回が初合わせだった『GR』。
初回だからなかなかうまくいかないことは多々あります。
何度もやっていくうちにまとまってくることが多いです。
が、今のうちに矯正しておかないと、
できないままになってしまいそうな箇所があります。
それはリハーサル記号「25」ゾーンと「34」ゾーン。
主に金管楽器とスネア・ドラムが1拍を3分割する三連符を演奏する場面で、
木管高音域の楽器は半拍を3分割する三連符を演奏しますが、
後者のリズムが前者につられて、1/3拍を3分割してしまう傾向にあります。
実に演奏しにくいリズムです。
まずはリズムの「理屈」を頭に入れて、
その上でリズムの「感じ方」を体に覚えさせて、
反復練習する。
という過程が必要かと思い、
第1ステップのリズムの「理屈」を説明しようと思って、
三連符の図を用意していました。
4/4拍子の、1拍だけを抜き出したものです。
図の下半分が、1拍を3分割する三連符。
上半分が、半白を3分割する三連符です。
赤の点線で、リズムの合致するポイントを示しました。
この図を見て、すぐ理解できる人もいれば、
「?」の方もいらっしゃるかなと思います。
じっくり考えると分かってもらえるでしょうか。
下半分の三連符を、六連符にすると分かりやすいんですが、
逆に混乱するかも知れないので、
この場ではやめておきます。
『GR』は演奏時間が20分弱かかりそうな大曲ですので、
暫くは基本練習、コラール練習をしたら、
『GR』にかかりっきりになるかと思います。
( K さんのコラールの新作を、コラール練習とは別に挟み込みたいとも思ってますが)
次回の合奏で、この三連符について、再び解説したいと思います。
(今回は楽員向けオンリーの内容となってしまいましたな)